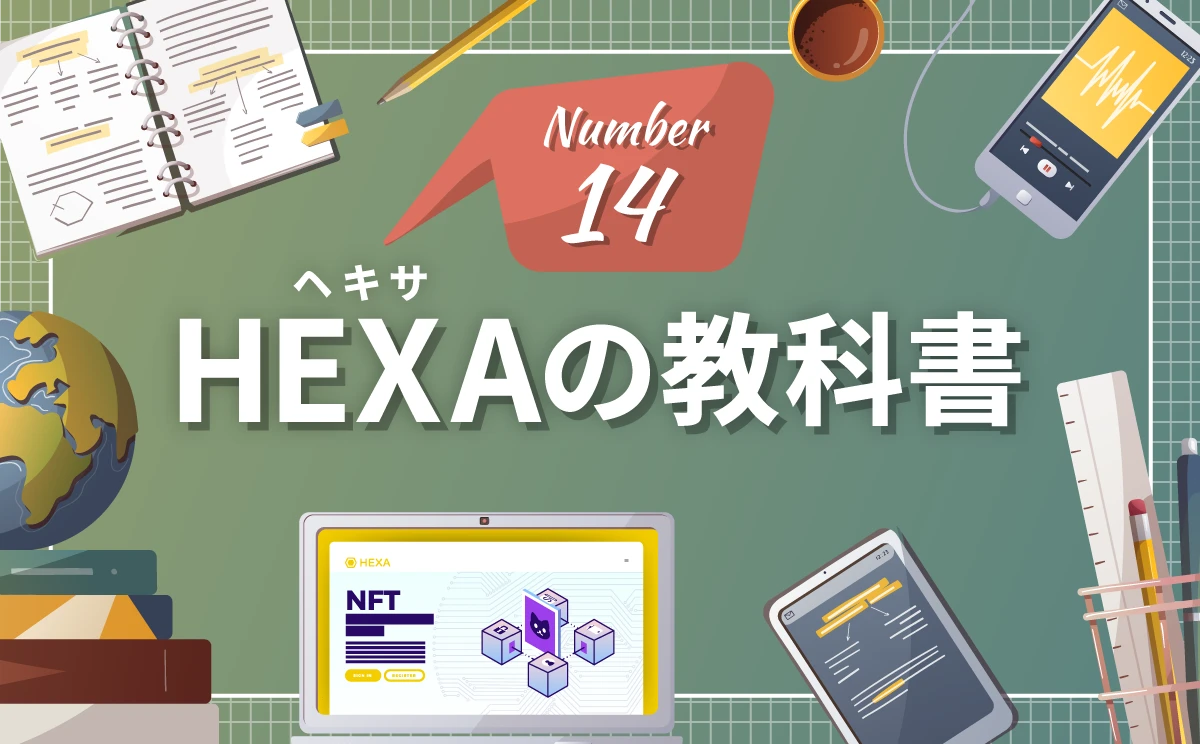AI・メタバース・ゲームに精通し、多くの商業Webメディアへの寄稿するライターでありながら自身もVTuberとして活躍する「咲文(さきふみ)でんこ」さん。ご自身もバーチャル住民としてcluster、NeosVR、VRChatといったさまざまなプラットフォームで生活中。イベントMC、ラジオパーソナリティ、DJなど多岐にわたる活動を通し、メタバースの魅力を発信されています。MetaStepにもコラムをご執筆いただいております。今回はその第2弾。それではでんこさん、お願いします!

咲文(さきふみ)でんこ
AI・メタバース・ゲーム業界を追うフリーライター/ジャーナリスト。ゲームライターとしてキャリアをスタートし、テクノロジーの進化と共に取材領域を拡大している。また、ライティングの傍ら、VTuberとしても活動中。
「生成AIにより仕事が奪われる」。そういった懸念をSNSなどでよく目にします。
確かに、文章生成AIでレポートやブログ記事も生成できますし、画像や動画といったビジュアルコンテンツ、音楽、Webサイト、その他多くのデジタル作品を生成するAIが既に存在しており、今後も増加することでしょう。そういった状況から、特にクリエイター系の職種からは生成AIに反対の立場を取る人の気持ちもわかります。
他人事のように書いていますが、私のようなライターも仕事が奪われると言われている職業の1つです。ですが、私は仕事を奪われるといった未来は来ないと思っていますし、むしろ生成AIにより仕事のクオリティが上がったり、省力化ができたりすることによって、創作の幅は広がり、人類がより豊かになっていくと考えています。
今回は私が考える、AIによりもたらされる人類が豊かになっていく未来について考えていきます。
歴史から学ぶAI革命が人類に与える影響
「AIが人間の仕事を奪い、職を失う人が多く出る」とよく言われていますよね。それは起こりうる未来なのでしょうか。私は「一部のタスクがAIに置き換えられる」と考えています。確かに、AIによって代替されるタスクや職業はあるでしょう。ですが、これまでも技術の進歩により機械やコンピューターに代替されてきた職業はたくさんあります。
自動改札機の普及により、改札の仕事が減ったのは間違いないでしょうし、電話交換手の仕事もなくなりました。遡れば移動手段の進化により飛脚といった職業もなくなりましたね。ほかにも技術の進歩によりなくなったり、変化した仕事は多く存在します。
それでは人類全体の仕事は減ったのでしょうか。そうではないですよね。なくなった職業もあれば新しく生まれた職業もあります。それは人類史で何度も繰り返されてきました。
新しい技術により、新しい職業が生まれ、新しい働き方が生まれるのです。イメージしやすいのはインターネットの普及でしょうか。今でこそ当たり前ですが、eメールや、メッセンジャー、SNSを使った情報のやりとり、クラウドワークやフリーランスといった働き方の変化があったことは周知の事実ですよね。
直近ではそのインターネットをさらに使ったZoomやTeamsといったツールによるビデオ会議も当たり前になり、リモートワークという働き方が普及しました。そういった働き方の変化の流れを考えると、今後はAIの普及によって新しい働き方が生まれると私は考えます。
ただ、これまでのさまざまな革命的な技術の進歩と異なる特徴は、その変化のスピードと、影響を受ける職業の広さにもあります。これまでの技術革新では主に肉体労働や単純作業が自動化されてきましたが、AIは知的労働や創造的な仕事にまで影響を及ぼします。弁護士、医師、教師、プログラマー、デザイナーなど、高度な教育を受けた専門職でさえ、その一部の業務はAIによって効率化される可能性があります。
しかし、こうした変化は必ずしも職業がなくなるわけではありません。むしろ、仕事の内容や求められるスキルの変化をもたらすことでしょう。
例えば、弁護士は単純な契約書作成よりも、複雑な交渉や戦略立案に注力できるようになり、医師は診断をサポートするAIを活用しながら、患者との関係構築や複雑な治療判断に集中できるようになるでしょう。
このように、AIの発展は職業の消滅ではなく「職業の進化」や「働き方の変化」をもたらすと考えています。私たちに必要なのは職業の消滅を恐れることではなく、この変化に適応し、AIと共存する新しい働き方を見つけることです。
人間の能力をサポートするAIの可能性
私は現段階においては、AIはあくまでも人間の能力をサポートしてくれる存在だと考えています。
AIのフォローによりタスクのクオリティが上がり、人間が創造したイラストや音楽などのクリエイティブを拡張するサポートをしてくれる。さらにそこから新しいインスピレーションが生まれて新たな創作物が生まれることもあるでしょう。
現時点ではAIによる生成物はそのまま使用できる完成度ではありません。それは普段から文章生成AIを使っている私も強く実感しています。ですが、タスクのサポート手段としては非常に有用です。
ライターの仕事の範囲でも、アイデア出しや誤字脱字のチェック、表現手法のアイデアを提案させることなどに活用しています。こういった用途だけでも、表現の幅が広がっていることは強く感じています。
そのため、この先のAIと人間の関係性は「代替」ではなく「協働」が基本となるでしょう。AIは私たちの創造性を奪うものではなく、むしろ新たな表現の可能性を広げるツールなのです。
例えば、音楽家がAIを使って新しい音楽を探索したり、作家がAIとのやり取りから新しい物語のアイデアを得たり、デザイナーがAIの生成した案をたたき台にして独自の視点を加えたりすることで、これまでにない独創的な成果物が生まれる可能性があります。
しかし、この協働を実現するには、AIのできることとできないことを正確に理解し、人間にしかできない判断や感情、倫理観、文化的背景の理解などを大切にしていく必要があります。AIはあくまでツールであり、最終的な判断や責任は人間が持つことを忘れてはなりません。
それらを踏まえて、AIとの協働を進めるためには何が必要でしょうか。それは、今から積極的にAIを使うことです。AIをたくさん使うこと、そして使い方の例を見ることで、AIと協働するための創造力も養われることでしょうし、AIの長所・短所・問題点なども理解できます。
前述したとおり、AIは完璧な存在ではありません、ですが、AIのサポートにより効率化される業務は多岐に渡ります。これまでの人類史でもさまざまな作業やタスクをサポートしてくれる道具が生まれました。ですが、どんな道具も触り初めからいきなり完璧に使いこなせるモノではありませんよね。道具を徐々に使っていくことで、最適な活用法や使い方のコツが見えてくるのです。それはAIも変わりません。
 (引用元:photoAC)
(引用元:photoAC)
AI時代における生産性革命
そもそも人類史は効率化の歴史であると言えます。
道具の発明から産業革命、そしてデジタル革命に至るまで、人間は常に作業の効率を高め、より少ない労力でより多くの成果を得ようと努力してきました。
GDPという視点で見てみましょう。産業革命によりそれまで安定していた1人あたりのGDPが増加しました。つまり、1人当たりの生産性が上がっていったのです。
生産性が上がるとどのようなメリットがあるのでしょうか。日本では今後労働人口の減少が予測されています。総務省のレポートでは「2050年には5,275万人(2021年から29.2%減)に減少すると見込まれている。生産年齢人口の減少により、労働力の不足、国内需要の減少による経済規模の縮小などさまざまな社会的・経済的課題の深刻化が懸念される。」というレポートが出ています(参考:特集 情報通信白書刊行から50年~ICTとデジタル経済の変遷~)。このような状況下でも、少ない労働人口で生産性を維持する必要があり、AIによる生産性向上は必須と言えるでしょう。
アクセンチュアによる分析では、「日本では2035年にAIの普及により労働生産性がベースライン比で34%向上する」としています(参考:特集 進化するデジタル経済とその先にあるSociety 5.0)。この数字が示すように、AIは私たちの労働生産性を大きく向上させる可能性を秘めているのです。
AIの普及によりなくなる仕事は確かにあるでしょう。事務処理の一部や、基本的な翻訳業務などはある程度の影響を受けるかもしれません。さらに、例えば音声生成AIと文章生成AIを組み合わせたコールセンターのようなサービスが生まれると、影響を受ける範囲はさらに広がるでしょう。
ただ、AIの発展によりなくなる仕事が生まれる一方、AIによるサポートでさらに効率が上がる仕事も増加していきます。ライターという職業に限っても、インタビューの文字起こしなどの作業がAIの力でサポートされ、効率が大きく上昇しました。
こうして生まれた時間でさらに仕事をすることもできますし、仕事から離れて家族と過ごすための時間に充てることもできます。もちろん、副業などをすることもできるでしょう。AIにタスクをサポートさせることで、個人の生産性が上がっていくのです。
つまり、AIの活用による効率化は、私たちの働き方やワークライフバランスにも良い影響をもたらす可能性があります。
AIによる生産性革命は、単なる経済的効率化を超えて、私たちの働き方や生き方そのものを変える可能性を秘めています。その変化を前向きに捉え、AIと共に進化する社会を構築していくことが、これからの私たちの課題ではないでしょうか。
AIと人間の協創がもたらす未来の可能性
そして、芸術分野においても、AIの登場により大きな変革が起きています。画像生成AI、音楽生成AI、文章生成AIなど、さまざまな創作活動をサポートするテクノロジーが急速に発展していますよね。
例えば、ミュージシャンがAIを使って新しい音色やメロディを試し、それを土台に独自の楽曲を作り上げる。作家がAIとの対話から物語の新しい展開やキャラクターの可能性を見出す。映像作家がAIで生成した映像を素材として、これまでにない表現を模索する。こうした「人間×AI」の協創は、クリエイティブ自体を拡張し、新たな芸術形態を生み出す可能性があります。
歴史を遡ると、芸術分野に影響を与えた技術の1つとして、カメラの登場が挙げられます。カメラの登場により、画家達の作品に影響を与えました。写実主義の画家はもちろん、印象派の画家にとっても新しい表現のアプローチを開拓しました。
身近なところに置き換えるとコンピューターの登場もそうでしょう。コンピューター上でイラストを描くこと、コンピューター上で作曲をすること、今ではそういったことが当たり前になりました。さらに、「知の高速道路」とも言われるインターネットの登場により、創作のノウハウが一気に広がる時代になりました。
このように時代の進化により新しい創作の手段が生まれ、創作の可能性も加速していったのです。創作の新しい可能性が、AIが身近になった未来の芸術家の表現にも起きるでしょう。
AIは決して人類の創造力を奪う存在ではありません。人類の創造力を加速させる存在だと私は思います。インターネットが「知の高速道路」ならば、AIは「創造力のエンジン」と言えるかもしれません。
専門的なスキルや長年の訓練がなくても、AIのサポートによって個人が自分のアイデアを具現化できる。これにより、より多くの人々が創作に参加できるようになり、多様な視点や表現が生まれる土壌が広がるでしょう。
今はその過渡期で、そういった時代には混乱が生まれるのは当然です。その混乱を乗り越えた先には、労働が効率化された新しい職業や、創造性が拡張した新しい創作物、そこから新たな文化が生まれることでしょう。
AIの発展や広がりはもう止まることはありません。私たちはAIが発展し広がる未来を恐れるのではなく、AIとどのようにして協働していくか、自分の専門分野にAIをどのように活用するか、どのようにAIを活用して生産性を上げていくか。そういったことに注目していく必要があります。
そうして生まれる、人類全体の生産性が上がり、人類の創造性が解き放たれた未来。その世界が来た時こそが、AIにより人類が豊かになった世界でしょう。