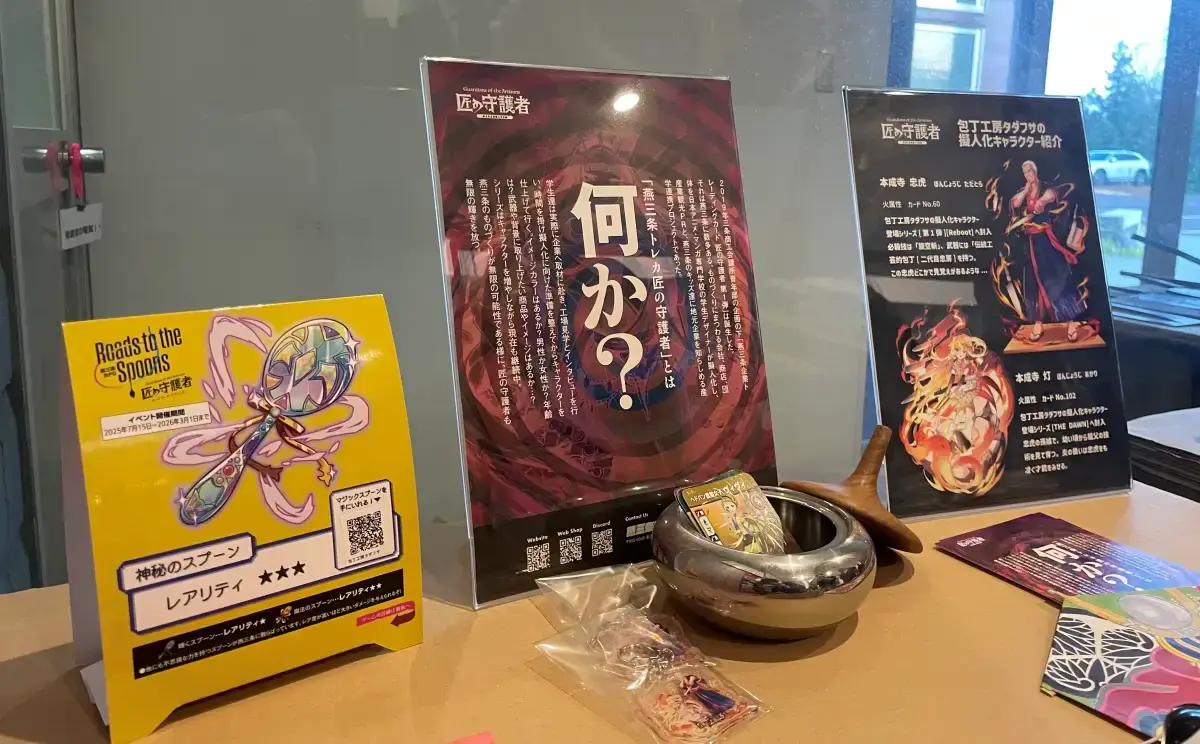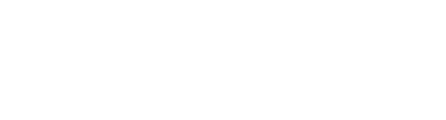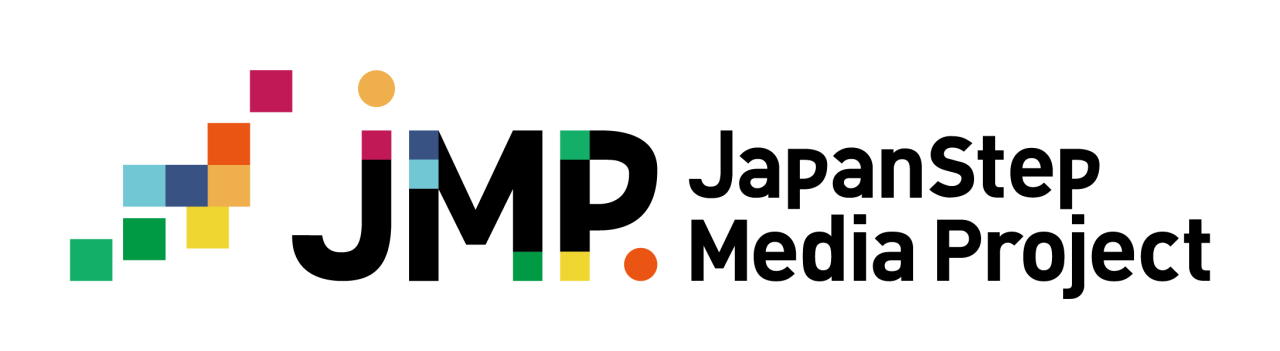メタバースの議論は「仮想空間の話」から、「人が集まり、関係が続く場をどう設計するか」へ移りつつある。その転換点を象徴するのが、没入型ソーシャルプラットフォームVRChatの急成長だ。2025年12月17日、VRChat Inc.主催として日本初の公式ビジネスオフラインイベント「VRChat Japan Business Experience 2025」が秋葉原で開かれ、米国本社の経営幹部と日本の責任者が登壇した。熱量の源泉はどこにあり、企業のビジネス活用にどんな打ち手をもたらすのか。(文=MetaStep編集部)
熱狂する日本市場と「IEM」が示す指針
講演の冒頭、VRChat Business Development Japanの北庄司 英雄さんは「VRChatをやっている方はどのくらいいますか?」と会場に問いかけた。想像以上の挙手に、思わず「本当に驚きですし、すごいですね。本日のイベントが普通ではないということがよく分かりました」と率直に驚きを漏らした。実際、VRChatの熱心なユーザーに加え、ビジネス活用の可能性を探る来場者も多く詰めかけており、急成長のVRChatを印象付けた。

北庄司さん自身も2024年7月にVRChat Inc.に参画し、日常的にVRChatを利用しているという。VRChatは米国に次ぐ第2位のユーザー規模で、主要層は16〜34歳。2025年の年始には同時接続数が13万6,000人を記録し、VRChatが「メディアとして成立する厚み」が増していると語った。成長を押し上げる要素として、9月のiOS版リリースを挙げた。数値の開示は控えつつも、「ダウンロードは順調に伸びている」とし、VR機器やハイエンドPCが前提だった層以外へ入口が広がった点を強調した。

講演で、北庄司さんはVRChatを改めて「没入型ソーシャルメディア(IM)」として整理した。単なるVR空間でも、単なるSNSでもない。身体性を伴う没入が、コミュニケーションそのものを「体験」へ押し上げる——ここにVRChatのコアがある、という捉え方だ。
では企業は、何を設計すべきか。北庄司さんが提示したのが、没入(Immersive)×体験(Experience)×マーケティング(Marketing)というフレームワークだ。稟議や企画書に落とす際、従来の「広告」「イベント」だけで語ると、社内合意が途切れやすい。だが、没入が生む「記憶に残る体験」を中心に据えると、目的と手段が一本の線でつながりやすくなると説明。「稟議書を書く際にも、是非そういったメッセージを入れることで、社内意思決定が進むと嬉しい」と北庄司さんは期待を語った。

「第三の場所」が定着を生む設計
続いて登壇したのは、VP of Product, Design & Productionを務めるケイシー・ウィルムズさん。話の軸に置いたのは、「第三の場所(Third Place)」というキーワードだった。家でも職場でもない、気を抜けて人とつながれる「居場所」。ウィルムズさんはVRChatを、そこに位置づける。

自らもVRChatに入っているウィルムズさん。当初は楽しみ方が分からず戸惑ったという。転機として挙げたのが、日本のユーザーが作ったワールド「ポピー横丁」。路地を進むとバーがあり、入った瞬間に「いらっしゃいませ」とリアルさながらのシチュエーション。席に着くとビールが出てくる。会話が始まると、気づけば「飲んでいる感覚」まで立ち上がってきた。「バーチャルだけどビールが美味しく感じてしまって(笑)。でも、それくらい楽しかった」(ウィルムズさん)

この「場としての価値」を示す材料として語られたのが、2024年に日本で起きたストリーマーブーム後の分析だ。ブームにより新規が流入したあと、「戻ってくる」初心者の割合が日本で最も伸びたという。理由を掘ると、視聴で遊び方を理解した初心者が、友達とつながり、グループに入り、会話(ボイス/チャット)を増やしていった。つまり「ソーシャルの経験」が増えた人ほど残ったという。
「日本では、共通の『ソーシャルなマナー』があります。礼儀正しく、会話は丁寧で、周りを気遣う文化もある。だから、VRChatは多くの人にとって『オンラインの第三の場所』になっています」(ウィルムズさん)

その学びをプロダクトに反映する例として、イベントを見つける「Live Now」、興味に合う集団へ入れる「Group Discovery」、共通のつながりを手がかりに人を見つける「Shared Connections」を挙げた。第三の場所は自然発生しない。見つけやすく、入りやすく、続けやすい導線を「機能として」用意しているという。
さらに、第三の場所が大きくなるほど、外出前に服を選ぶように、アバターやファッションを選ぶ文化が育つ。ウィルムズさんは「出かける準備が大事」と語り、アバターファッション誌の存在にも触れた。「現実と同じように、VRChatでも第三の場所に出かける前に、『服とアクセサリーを選ぶ』のが当たり前になりつつあります」(ウィルムズさん)

「いまは、『数年に一度』ではなく、数か月ごとに新しい波が来ている」と語ったウィルムズさん。「今後、ユーザーだけでなく、パートナーやファンにとっての第三の場所として、プラットフォームに『場』を用意していきます」と、力強い言葉で締めた。
B2B2Cで広がる事業機会の具体像
基調講演の最後に登壇したVP of Operations & Legalのジェレミー・ウィールフェルダーさんは、企業連携の視点から、VRChatがビジネスに開いていく理由を語った。

最初に強調したのは、日本の位置づけだ。日本は長年にわたり、VRChatの中でも創造性と熱量が高いコミュニティの一つであり続けている。日本のパートナー、クリエイター、コミュニティが、ソーシャル・イマーシブ・プラットフォームの未来を形作っている——この前提を置いたうえで、今後も日本への投資を続け、取り組みを広げていく考えを示した。
続いて提示したキーワードが「B2B2C」だ。VRChatはコンシューマー向けの会社だが、ビジネスパートナーが入ることで、ブランドやIPホルダーがユーザーと出会い、体験を共にし、関係を継続する回路が生まれる。企業側のメリットは大きく三つに整理された。新しいオーディエンスへのリーチ、既存コミュニティとの新しい関係づくり、そして収益機会、だ。逆にVRChat側は、パートナーが魅力的なコンテンツやIPを持ち込むことで、既存ユーザーを惹きつけ、新規ユーザーの獲得と定着を進められる。双方の成長が連動するモデルといえる。

機会領域は、イベント、マーケットプレイス、没入型の広告キャンペーン。ゲーム、アニメ、ファッション、音楽といった産業は、象徴的なキャラクター、熱心なファン、豊かな世界観をすでに持っている。VRChatが加えられるのは、「身体性・コミュニティ・プレゼンス(存在感)」だ。ファンは「見る」から「一緒に体験する」へ移る。ここを、次世代のIPアクティベーションの舞台として捉えている。
具体策として紹介されたのが、VRChat Shopを起点にした展開だ。新しいコンテンツタイプはまずShopでリリースし、その後UGCへ広げるかどうかを慎重に判断する。UGCの創造性を守りながら、企業やIPが参加しやすい形を整える狙いが見える。対象として挙がったのは、スポーン可能アイテム、ステッカー、絵文字、今後追加される各種コンテンツタイプ。さらに、ワールド公開やアバター提供など「Seller」としての参加、ショップ全体をテーマ化する「マーケットプレイス・テイクオーバー」、アバター用アクセサリー制作など、複数の連携の形が示された。

広告面の例として挙げたのは、映画「TRON: Ares」公開記念の「VR渋谷」ワールド、月面に再現された「MOS BURGER ON THE MOON」、耐久テストを体験に落とし込んだ「G-SHOCK THE RIDE」。共通点は、露出ではなく「体験」を中心に設計していること。「体験が生まれると、参加が生まれ、語られ、次の来訪につながる」とウィールフェルダーさんは力を込めた。
終盤には、イベントのチケッティングが要望として多いことにも触れた。現時点で確約はできないが、フィードバックがロードマップに反映されていること、将来的に対応したい領域であることを明言した。そして2026年は、とくに「イベント」と「コンテンツ」に関する取り組みにパートナーを積極的に誘導していく方針だという。最後は、日本がVRChatの過去だけでなく未来においても中心であり続けるよう、強くコミットする、と結んだ。