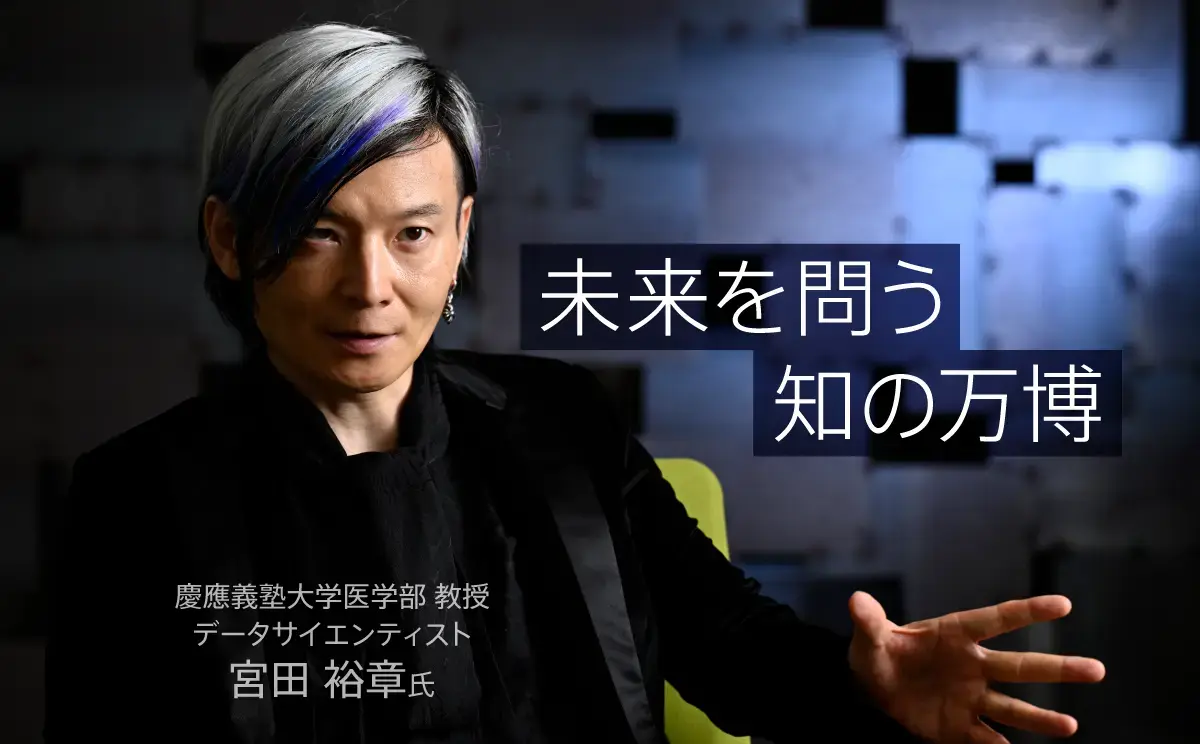東京大学生産技術研究所特任教授/建築家(NOIZ)豊田 啓介 氏
東京大学生産技術研究所特任教授/建築家(NOIZ)豊田 啓介 氏
会期中は大きな盛り上がりを見せ、様々な資産を残した大阪・関西万博。その中にあって、とりわけ存在感を示したのが、メディアアーティストの落合陽一氏がプロデュースするシグネチャーパビリオン「null²(ヌルヌル)」だ。このパビリオンの建築を手がけたのは、建築家で東京大学生産技術研究所の特任教授でもある豊田啓介氏。「null²」では、かつてないアプローチで「建築のエージェント性(生き物性)」に挑戦したという。万博という場だからこそ可能になった大いなる挑戦と、そこから見据える建築の未来について聞いた。(文=JapanStep編集部)
万博は「とんでもない機会」
豊田氏は2017年ごろから招致会場計画アドバイザーとして大阪・関西万博の会場計画のディレクションを担当し、大阪とパリでのBIEへの公式会場計画プレゼンテーションを担当するなど招致の段階からかかわってきた。「正直、最初のころは『今の時代に万博を開催する意義はあるのだろうか』という懐疑的な気持ちがありました」と語る。しかし、万博は建築にとって、他にはない機会であると思うようになったという。
「情報技術がものすごいスピードで進歩していますが、実空間、特に都市や建築と情報をつなげて実証実験をする場が、日本では決定的に不足していると感じていました。その点、万博は住民のしがらみがない場所で半年間にわたって仮設の実証実験都市を運営できる『とんでもない機会』だと気づいたのです」(豊田氏)
かつてない建物を生み出す 「null²」の挑戦
豊田氏は誘致会場計画アドバイザーとしての役割を終えた後、落合陽一氏からの依頼を受けて「null²」の設計に関わることになった。「落合さんとは何度も仕事をやっていたので、彼がつくりたいイメージはなんとなく分かりました。金属質でドロドロっとした感じ。当時はまだ『ヌルヌル』というキーワードはなかったですが、そういうのをやりたいのだろうなと。また、落合さんとやる以上は、『建物を動かすことになるよね』と。最初から動くというのは共通認識としてありました。そこで、動かすことを前提にしてチームが組まれていきました」(豊田氏)
 撮影:阿野太一
撮影:阿野太一
万博の建物は、中で披露するコンテンツが固まる前に着手しなければ間に合わない。さらに、コストも潤沢でないだろうことは当初から予見された。「予算や機能の変更に対応できて、なおかつ、建築の強度が弱まらない。むしろ変更すればするほど強くなる設計システムにする必要がありました。それを前提にした時、Anish Kapoorの彫刻のように本物の金属で造形していたら対応できない。そこで、膜で金属的な柔らかい面をつくれないかと考えました。急ぎ、膜構造の世界最大手である太陽工業さんを最初に捕まえて、『金属膜の開発から一緒にやるので最後まで付き合ってほしい』とお願いしました。金属質の光沢を持ちしかもやわらかい膜を目指して、1年半かけて、銀色で98%反射する鏡のような膜をつくりあげました」(豊田氏)
次に、「null²」には建築チームとしてのNOIZやARUP、太陽工業以外にも、動的機構やビジュアルの専門チームもかかわっている。「実物大ガンダムの制作経験を持つ乃村工藝社や、ロボット制御システムのアスラテック、ビジュアルプロダクションのWoWなど、映像や物を動かす最先端のチームが当初から集まっていました。鏡面膜の内部に多数のロボットアームやウーファーなど複数のアクチュエーターを設置し、これらが膜を物理的に操作することで、建物の表面がさまざまな動きで絶えず変形します」(豊田氏)
このようにして、周囲の風景を変形させながら反射する、無機質なのに有機的な建築、「null²」が誕生した。
「『null²』建築の意図は、専門的に言えば『建築のエージェント性をどう実現するか』への挑戦です。これは『生き物のような建築』という概念に近いものですが、あえて生物と無生物の中間的な感じを目指しています。『null²』には目のようなものがあり、さらに絶えず揺れ動くので、見た人は本能的に生き物っぽさを感じます。無機質で、金属質で、どう考えても数学の図形やデジタルにしか見えない造形なのに、そこに生き物性を感じてしまうという心の動き。建物が本来持たないと思われていた自律性や生命感を、見る人にどれだけ感じてもらえるかというチャレンジでした」(豊田氏)
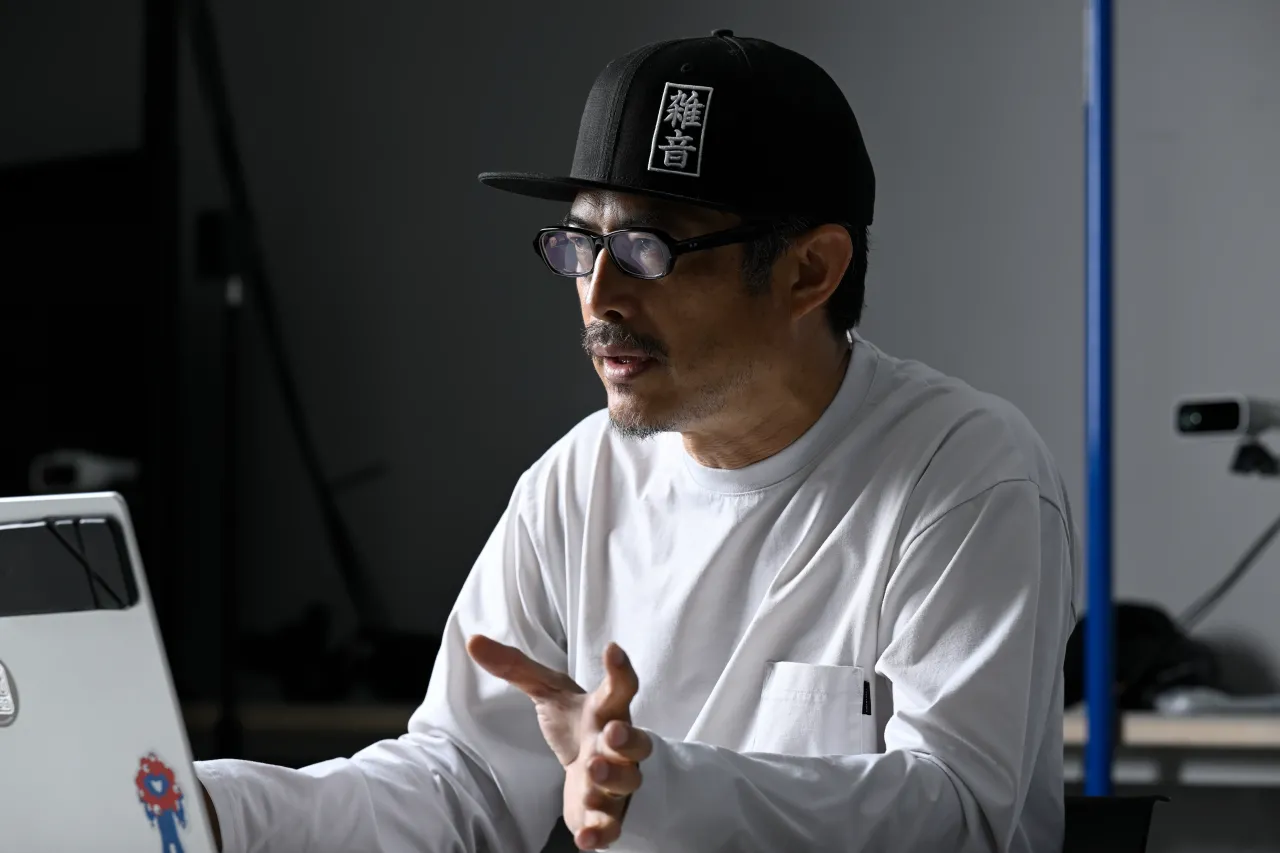
それまでに誰も見たことがないものをつくる。万博という場だからこそ可能になるシンプルな目的を「null²」は果たしている。出来上がった「null²」には、当初は予測していなかった魅力があったと豊田氏はいう。「今回、いろんなアクチュエーターやロボットアーム、音による波面合成で建築の形を作るようなこともやっているのですが、できてみて面白かったのは、自然の風による動きです。鏡面膜は大きくて重いので、風が吹いたときに、『タプン タプン』とゆっくりと動きます。僕はあの動きが実は一番好きで、そうした予想外があるのも建築の面白さだなと思っています」
 撮影:楠瀬友将
撮影:楠瀬友将
「null²」の不思議な造形。見た人に伝えたいメッセージを聞いた。「『null²』の造形としては、ラスボス感を出すというのもかなり意識してやっているので、いわゆる綺麗で可愛いものを狙っていません。『建築とはこういうもの』『美しさとはこういうもの』という概念を壊しにかかっているような建物です。その意味では、安定的な予定調和をそのまま感じるのとは違う感情が湧き起こってくれれば、それを大事にしてもらいたいです。それを『なんでだろう』と思う人がいれば、読み解けるところがたくさんある。建築には読み解き方の面白さ、さらに建築に閉じない読み解き方があります。その辺まで掘り下げていただけたら、すごく嬉しいです」
デジタル技術との統合によって進化する建築
万博での実践を経て、豊田氏は建築の未来をどのように見ているのだろうか。「様々なデジタル技術との統合によって、建築の役割は劇的に変化していきます。建築がデジタル情報やデバイスを備えることによって、より高いパフォーマンスを発揮する。建築はデジタル技術の没入型の基盤となり、社会における役割は、より一層大きくなっていきます」(豊田氏)
さらに、デジタル技術の探求は、必然的に建築と人間の境目を曖昧にするという。「建物が生き物らしさ、つまりはエージェント性をどのように獲得するのかという問いに、『null²』では挑戦しました。目指したのは、単純な生き物性の模倣ではなく、無機物が生き物になり始めた瞬間のような、無機物と有機物の境目を作り出すことです。膜が風によって『タプン タプン』と動くなど、無機物でありながら生き物性を感じさせる要素の新しい発見もありました。技術を突き詰めた先にこそ、より強く自然や生き物性を感じられる、新しい人間中心の建築の可能性があるのではないかと思います」
また、デジタル技術を介することによって、建築は20世紀のテレビ型(一方的な情報配信)から、ユーザーが編集・参加することができる n 対 n のSNS型コミュニケーションの場へと進化すると豊田氏は語る。「建築における n 対 n の関係性を作り出す条件や要素をきちんと試して、それを社会の共通の知識にしていくのが大切だと思います。今、我々はそこに挑戦しています。その意味で新しい環境で育っている世代の感性や感覚、彼らが持つ共有体験が生み出す可能性には期待したいですし、同時に建築や場所といった物理的な環境が備える、多くの人の蓄積された物語りや想いを強制的に束ねる力にも、あらためて価値を感じます。自分なりの解釈で感じて関わることができる新時代の建築を追求してほしいと期待しています」。万博という大いなる実践の場を経て、豊田氏の目は建築の未来を見据えている。デジタル技術が飛躍的な進歩を遂げる今、建築も大きく進化していくことだろう。
編集後記
「今の時代に万博は必要か?」という問いから始まった豊田氏の万博。結果的には、誘致の成功から話題のパビリオン「null²」の建設まで、完走しました。「null²」によって、「今まで誰も見たことがない建築をつくる」「建築の未来を見据える」という、万博だからこそできる挑戦が実現しました。そして、今回の万博も通過点の1つです。テクノロジーの進化によって、建築もまた大きく進化していく。ユーザーが参加・編集するという、新たな概念を持った建築に挑む豊田氏。今回の取材を通じて、建築の可能性は、今の時代だからこそ大きく広がっていることを感じました。