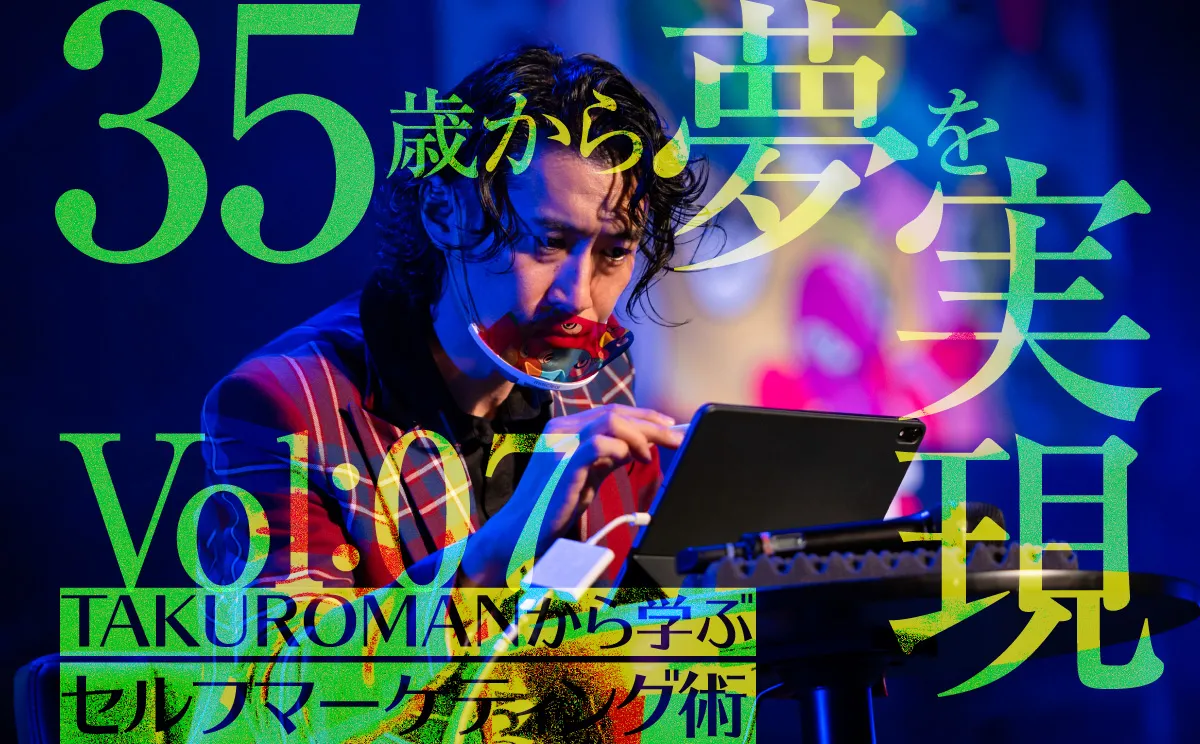(引用元:PR TIMES)
不登校の児童生徒数が過去最多を記録し続ける中、新たな学びの選択肢として注目を集めるのが、不登校の小中学生向けオルタナティブスクール「NIJINアカデミー」だ。2023年9月にオンラインで開校した同アカデミー本校は、メタバース空間を活用した双方向の学びや全国の仲間とのつながりを提供し、全国から累計で約480名以上が入学。保護者からは「子どもが本来の明るさを取り戻せた」と高い評価を得ている。
そして2024年からは、オンラインで元気になった子どもたちの「リアルでも学びたい」という声に応え、リアルキャンパスを全国に展開。その一つとして、2025年6月に東京都世田谷区に「世田谷駒沢校」が開校した。この新キャンパスにて、6月17日から26日 にかけて、新たな学びの形を体験できる「お料理体験会」が開催された。
世田谷駒沢校の教室長を務めるのは、子ども向けの料理教室「いちえと」を主宰してきた加納 静瑛 氏。「子どもたちが、自分らしくいられる場所をつくりたい」「違いを認め合いながら、安心して成長できる場を広げたい」という想いから、リアル校の立ち上げを決意したという。同校では、「何をしてもいい」を基本とし、子ども一人ひとりの「やりたい」を出発点にした自由な学びの場を提供。自分のペースで好きなことに没頭できる環境と、失敗しても受け入れられる安心感が子どもたちの主体性を育む。
今回開催される体験会では、旬の夏野菜をたっぷり使った「夏野菜先取りグラタン」作りを体験したほか、メタバースとリアル教室を組み合わせたハイブリッド学習の紹介や、保護者向けの説明会・個別相談会も行われた。

(引用元:PR TIMES)
メタバースとリアルが紡ぐ新しい教育と「居場所」の価値
NIJINアカデミーの取り組みは、不登校支援におけるメタバース活用の有効性を明確に示している。自宅からアバターを介して参加できるメタバース空間は、対人関係や特定の環境に強い不安を抱える子どもたちにとって、心理的な安全性が確保された社会参加への「第一歩」となる。アバターという存在は自己表現のハードルを下げ、顔や姿を見せることなく全国の同じような境遇の仲間との「つながり」を再構築する上で、極めて有効なツールだ。
さらに重要なのが、「オンラインからリアルへ」というハイブリッドモデルが持つ教育的意義である。オンラインのメタバース空間で自信やコミュニケーションへの意欲を取り戻した子どもたちが、次のステップとしてリアルな場での交流や体験を求めるようになる。今回のお料理体験会のようなリアルイベントは、五感を使った学びや仲間との共同作業といった、バーチャルだけでは得難い複合的な体験価値を提供する。この「メタバース⇆リアル」の往還は、子どもたちがそれぞれのペースで社会との接点を段階的に広げていくための、非常に柔軟で理想的なスモールステップと言えるだろう。
「何をしてもいい」という自由な学びの理念も、このハイブリッドモデルと深く結びついている。画一的なカリキュラムではなく、子どもの内発的な興味・関心を尊重する姿勢は、メタバース空間で多様なワールドを探検したり、リアルな場でさまざまなプロジェクトに挑戦したりといった主体的な学びを促進する。子どもたちが「どうせ無理」ではなく「ちょっとやってみようかな」と前を向くようになるのは、まさにこの安心できる「居場所」があるからだ。テクノロジーの活用もさることながら、失敗を恐れずに挑戦できる環境こそが子どもの自己肯定感を育む上で最も重要であることを、この事実は示している。
NIJINアカデミーの取り組みは、不登校という社会課題への対応に留まらず、これからの教育全体のあり方をも示唆している。メタバースやAIといった先端技術を活用しつつ、リアルな体験や人との温かい繋がりも重視するハイブリッドな学びの形は、既存の学校制度の枠に収まらない、多様な選択肢を持つ「学びのポートフォリオ」を社会全体で構築していく必要性を投げかける。NIJINアカデミーは、メタバースを単なる目新しいツールとしてではなく、子どもたちの心に寄り添い、社会と再び繋がるための「優しく、力強い架け橋」として活用する先進的なモデルケースだと言える。