「インタラクション設計」とは、ユーザーの操作に対して、製品やサービスがどのように反応するかを設計することを指します。あらゆるデジタルサービスに通ずる言葉ですが、メタバースにおいては、操作時の挙動や、現実世界との間で、どのように情報をやり取りするかといったところが挙げられます。
この点を考える必要性は、メタバースを構築する人だけに限りません。メタバースに関わるビジネスをする方にとっても重要で、「メタバースで何をしたいのか」考えるうえで外せない事項です。まずは本記事で簡単に解説しますので、ここから考えるきっかけを得て貰えたらと思います。
メタバースのインタラクション設計とは?
メタバースにおけるインタラクション設計とは、ユーザーがバーチャル空間内でどのように各種操作を行い、他のユーザーやオブジェクトとどう関わるかを設計する技術です。現実世界での行動様式を活かしつつ、デジタル空間ならではの新しい操作体験を創り出すことが求められます。
優れたインタラクション設計は、ユーザーが「◯◯をするためには、どうすればいいのか」と考えることなく、直感的に操作できる環境を実現します。初めてメタバース空間に訪れるユーザーでも迷わず操作できることが、普及の鍵を握っています。
メタバースにおける主なインタラクションの種類
メタバース空間での代表的なインタラクション方法を見ていきましょう。これらは単独で使われることもあれば、複数の方式を組み合わせて使われることもあります。
コントローラー操作
 (引用元:Unsplash)
(引用元:Unsplash)
VRコントローラーやゲームパッドなどの物理デバイスを使った操作方法です。ボタンやスティックで操作し、物をつかむ、投げる、選択するなどの動作が可能です。触覚フィードバック(振動など)により、バーチャル空間での触感を再現できる点が特徴です。
視線操作
ユーザーの視線や頭の向きを追跡し、見ている対象に対して操作する方法です。長く見つめる、まばたきするなどの動作を組み合わせて選択操作を行います。手が使えない状況でも操作できる利点がある一方で、誤操作防止の工夫も必要です。
ジェスチャー認識
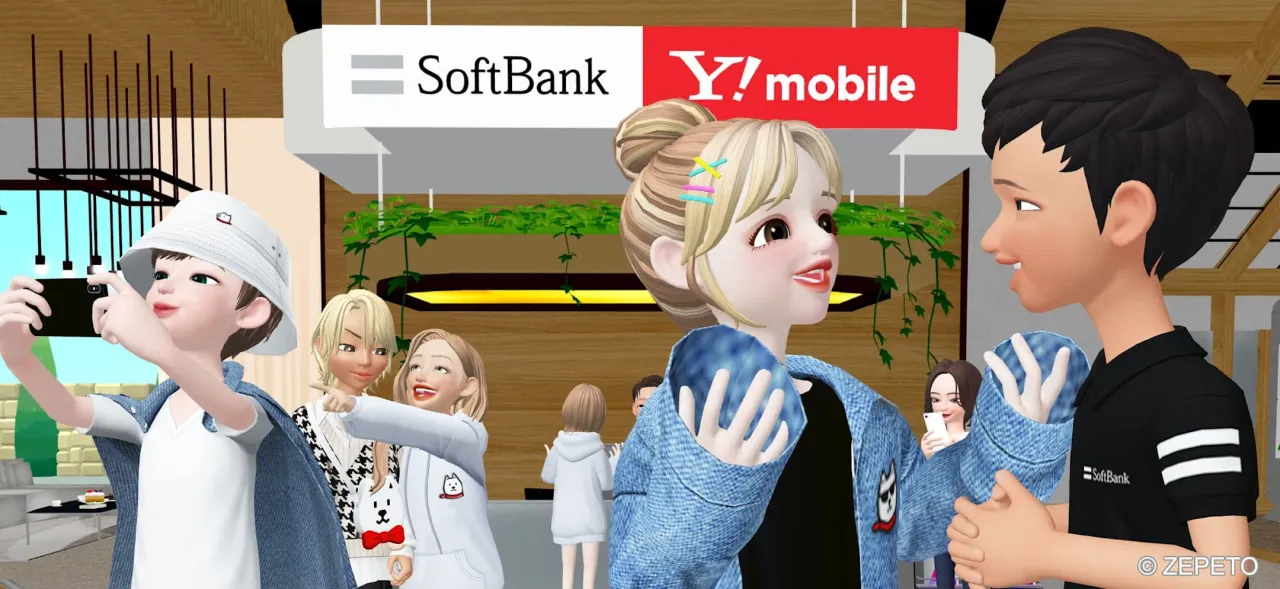
(引用元:知財図鑑)韓国発のメタバース「ZEPETO(ゼペット)」。充実したファッションアイテム等を使った自己表現が売りだ
手や体の動きをカメラやセンサーで認識し、操作に変換する方法です。手を振る、指でピンチイン・ピンチアウトする、腕を伸ばすなど、自然な動作でバーチャル空間を操作できます。専用デバイスを持たなくても良い利点がありますが、認識精度の課題もあります。
音声コマンド
話しかけることで操作する方法です。「移動して」「開いて」などの音声指示により、バーチャル空間での挙動を操作できます。両手がふさがっている状況でも使えるメリットがありますが、周囲の音やアクセントによる認識精度の問題があります。
直感的なインタラクションを実現するポイント

(引用元:PR TIMES)世界初のメタバース内360°VR広告を提供するThe360合同会社
メタバース空間でユーザーが迷わず操作できるようにするためには、いくつかの重要なポイントがあります。これらを押さえることで、初心者でもストレスなく利用できるインターフェースを実現できます。
現実世界での経験や動作を活用する
現実世界での経験を活かした設計は、ユーザーの学習コストを下げます。例えば、ドアを開けるには取っ手を回す、物を移動させるにはつかんで動かすなど、日常の動作に近い操作方法を取り入れることで、メタバース内での操作方法もスムーズに理解できます。
フィードバックを明確に行う
ユーザーが行った操作に対する反応(視覚、聴覚、触覚など)を明確に提供することで、ユーザーは自分の行動の結果を理解できます。ボタンを押したら色が変わる、音が鳴る、振動するなど、複数の感覚に働きかけるフィードバックが効果的です。
一貫性を保つ
メタバース空間全体で操作方法に一貫性を持たせることで、ユーザーは一度学習すれば応用できるようになります。例えば、「つかむ」動作が場所によって異なると、操作方法を何度も覚え直す必要があるため混乱を招きます。
わかりやすい手がかりを設計する
「このオブジェクトはこう操作できる」という手がかりを視覚的に提供することで、ユーザーは理解しやすくなります。例えば、つかめるオブジェクトは少し浮かせる、インタラクティブな要素は光らせるなどの工夫が有効です。
ユーザーに“意識させない”インタラクション設計を
触覚フィードバック技術の進化や、脳波インターフェースなどの新技術により、メタバースでのインタラクション方法はさらに進化していくでしょう。しかし、技術が先行しがちな領域だからこそ、「人間中心の設計」という原則に立ち返ることが重要です。
将来的には、ユーザーがインターフェースの存在を意識せず、自然に目的を達成できる「シームレスなインタラクション」が理想形と言えるでしょう。メタバースの普及とともに、インタラクション設計の重要性はますます高まっていきます。












