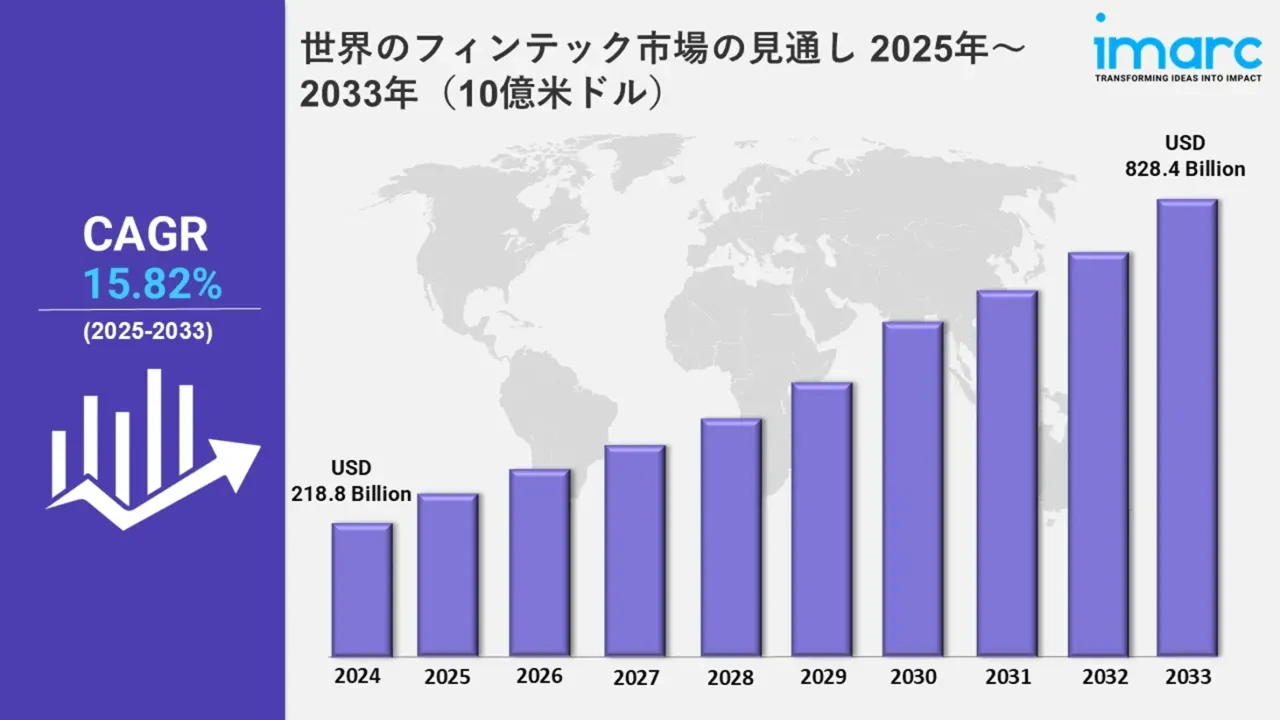ここ数年AIを始め、XR、Web3、メタバースの各分野の発展はめざましいものがある。しかし発展を喜ぶ一方で、各分野は法整備すらままならず、グレーゾーンも存在するといった状態で、誰もその勢いを止められないでいる。ビジネス活用を推進する我々MetaStepとしては、現状を冷静に分析し、法的観点から各分野を考えていく必要がある。
そこで我々は、JapanStepプロジェクトを後援いただいているガンマ法律事務所に寄稿を依頼。同事務所は、サンフランシスコとニューヨークにオフィスを構える法律事務所。最先端のWeb3・XR・メタバースの専門知識を有し、メディアやエンターテインメント・テクノロジー業界に精通している。
各業界のスタートアップから、国際的な著名度を有するメディア企業や大手ゲーム企業まで多岐にわたる支援を行ってきた同事務所は、法的観点から各分野を考察するコラムを自社掲載中。MetaStepにも掲載を頂けることに。第1回は「メタバースのアバターは人間か、ピクセルか」。ぜひご一読頂きたい。

ガンマ法律事務所 代表弁護士(マネージング・パートナー)
David Hoppe(デイビット・ホッピ)
デジタル・メディア、ビデオゲームとバーチャル・リアリティーを専門分野とし、最先端のメディア、テクノロジー関係の企業を、30年近くクライアントとしてきた。洗練さと国際的な視点を兼ね備え、スタートアップ業界、新興企業、またグローバル化使用とする企業の現実を、実践経験から理解する国際的な取引交渉弁護士として活躍。世界各国に事務所を置く国際的弁護士事務所Jones DayとWhite & Caseからキャリアをスタートさせ、NASDAQ上場のウェブ・ポータルであるExcite.comの国際弁護士を務め、日本のビデオゲームの出版社であるカプコンの北米ゼネラル・カウンシルとしての職務を務めた。
メタバース内のアバターは、ユーザーのデジタルアイデンティティを表現し、個人が仮想環境内を自由に移動したり、多様なインタラクションを行ったりすることを可能にします。アバターは、メタバース内のユーザーを体現するデジタル・ペルソナであり、ユーザーが自由にカスタマイズできるキャラクターです。これらのアバターは、リアルな外見やファンタジーのビジュアルや、さらには現実とフィクションを融合させた姿を反映するようにデザインされています。アバターを通じて、ユーザーは視覚的に自己表現をし、仮想環境と交流することができます。さらに、アバターを介して、ユーザーは歩いたり、話したり、物に触れたり、仮想の物体を所有したり、法的拘束力のある契約を結んだりすることも可能です。
つまり、アバターはメタバースにおける市民と見なすことができます。しかし、アバターに人格が認められるべきかという問題があります。AIの人格に関する法的な課題については過去の記事で考察しましたが、AIがどれほどの知覚能力を持っていたとしても、メタバースのアバターは人間のコントローラーの指示に従って行動する点で明確に異なります。
アバター: デジタル上のあなた
AIシステムは人間のような行動を示すソフトウェアプログラムですが、アバターは通常、実際の人間のデジタル表現や仮想的な具現化として存在します。デジタル表現の背後にいる人間はすでに人権を行使できるため、一見するとアバターの人格を考慮する必要はないように思えます。アバターが自律的でないことから、一部の論者は、アバターは「個人」ではなく、その指示を出す人間から切り離せないと主張しています。ただし、アバターはデジタル上で人間の代理として、外見や話し方、反応を自分の好みにカスタマイズすることが可能です。
このアバターをカスタマイズする能力は、デジタル空間における自己や他者の仮想表現をどのように認識し、どのように関与するかについて興味深い疑問を提起します。アバターは仮想世界における代理人としての役割を果たす一方で、現実世界での立場とはまったく異なる人格や役割を担うこともできます。メタバースにおける最終目標である相互運用性が実現すれば、アバターが同一人物として、さまざまな領域をシームレスに移動できるようになります。たとえば、私たちはある領域で仕事の一環としてプロトタイプのデモンストレーションに参加し、別のプラットフォームでラケットボールを楽しみ、また別の場所でバーチャルコンサートの最前列に座ることもできるのです。
しかし、メタバースのメガマインドが相互運用性を実現したとしても、サイバースペースで別の人格を維持することを好むユーザーも存在するでしょう。メタバースは、アバターに変身することで自己から離れる自由をを提供します。たとえば、企業の経営者は、経営者としての役割を演じるアバター、夜の副業を営むためのアバター、そして宇宙人の侵略から地球を守るアバターをそれぞれ作成するかもしれません。これらのアバターは独立して同時に存在しますが、法律上、それぞれを別々のバーチャルな「人格」と見なすべきなのでしょうか?
自由と責任
Web3のイノベーションの中心には、ユーザーに仮想アイデンティティやアバターへの前例のないコントロールを提供する分散型構造があります。しかし、この分散化は、ユーザーの自主性とアバターの行動に対する説明責任の間に複雑な緊張関係を生み出します。
メタバース内の社会的交流は、現実世界の交流を反映しています。アバターを通じて、ユーザーは他のユーザーとコミュニケーションを取り、協力し、交流を深めることができるため、仮想空間におけるコミュニティ意識や帰属感を育むことができます。しかし、この自由な表現や交流は、ユーザーの行動や責任能力に関する懸念も引き起こします。現実世界と同様に、メタバース内での行動は、個人や仕事上の人間関係、評判に影響を与え、場合によっては法的な問題に発展するなど、重大な結果をもたらす可能性があります。

メタバース内の経済活動は、ユーザーの管理と説明責任の複雑さを一層深める要因となります。アバターは、仮想商品の売買や仮想不動産市場への参加など、さまざまな商業活動に従事することができます。これらの経済取引ではしばしば仮想通貨が使用され、仮想世界と現実世界の資産の区別が曖昧になります。その結果、契約、財産所有権、金融取引に関する紛争が生じるリスクがあり、メタバース内での紛争解決や法的強制のメカニズムが求められています。
メタバースの分散型という性質により、責任の所在の問題は複雑化します。従来の規制枠組みは進化するデジタル環境に適応するのが難しく、仮想上のやりとりを監視する中央当局が存在しないため、ユーザーは権利、責任、結果の複雑な網の目を自力で進む必要があります。分散化によって、ユーザーは仮想上のアイデンティティに対してより大きな自主性を持つことができますが、一方でアバターの行動に対する責任を誰が負うのかという疑問も浮かび上がります。
メタバースにおける民事および刑事責任は、世界中の法制度にとって大きな課題となっています。管轄権の決定、契約の履行、仮想犯罪の起訴など、新たな法的ジレンマが生じており、革新的な解決策が求められています。さらに、アバターによる匿名性は、詐欺や嫌がらせ、知的財産権侵害といった違法行為を助長し、説明責任やエンフォースメントの問題を一層複雑化しています。
――ここから先はガンマ法律事務所にてご覧ください――