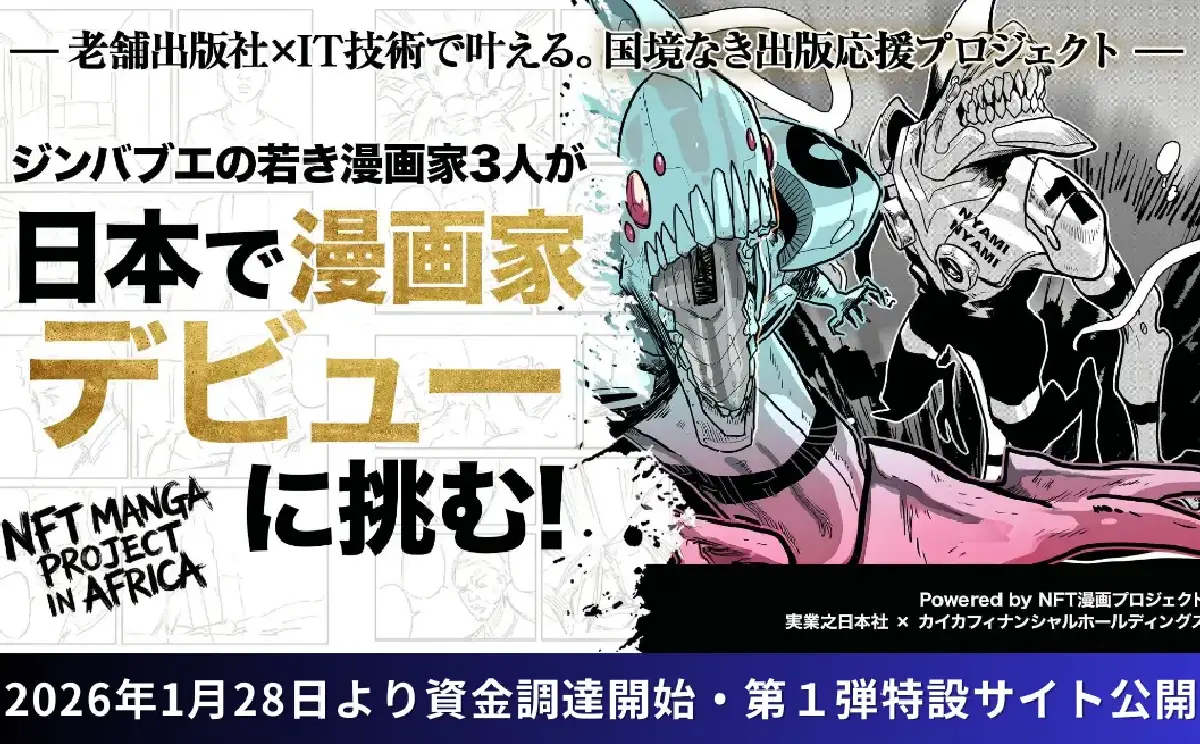メタバースより今はAIだ――。AIエージェントの登場や動画生成AIといった勢いに比べ、メタバースは鳴りを潜めていると感じる人も少なくないだろう。AIの発達によってあらゆる業界の可能性が広がっている中、今こそメタバース活用の在り方を改めて考える必要がある。今回編集部は、日本のメタバース業界団体最大手である一般社団法人Metaverse Japanが2025年2月20日に開催した第4期キックオフイベント「New Era of メタバース〜メタバースの未来とメタバースビジネスの行方〜」を取材。
東京・大手町で行われた本イベントでは、Metaverse Japanの理事を務めるパナソニック コネクト株式会社 取締役 執行役員 山口 有希子 氏、同アドバイザーの東京大学大学院 情報学環 特任准教授 小塩 篤史 氏によるスペシャルキーノートを実施し、メタバースへのAI活用について議論を交わした。AIの躍進はメタバースにとって追い風となるのか。(文=MetaStep編集部)
「どんな世界も作れる」AI、「どんな世界を作りたいか」問われる人間
ほとんどのメタバースが3DCGモデルを使用する中で、やはり注目されるAIは「3Dモデル生成」だ。例えば2024年7月にMetaが発表したAI技術「Meta 3D Gen」は、テキストから高品質の3Dモデルを生成できる。専門的なツールや技術を必要とせず、誰でも簡単に思い描いたイメージを3Dモデル化できるうえ、ライティングや質感調整もAIが自動処理。3Dモデルの制作にかかっていた時間とコストの大幅削減が見込まれる。
リアルタイムの自動生成技術にも転用される。従来のゲームやメタバースでは、あらかじめ用意されたコンテンツをユーザーが利用する形だったが、今後はプレイヤーの行動に応じて、想像したキャラクターやマップをその場で生成できる可能性もあり、実際に研究が進められているという。
モデリングだけでなく、メタバース内のキャラクターにAIを搭載し、実際に会話をしながらストーリーを進めるというインタラクティブな体験も実現できる。これは既に対話型バーチャルヒューマンにも応用されているため、イメージがしやすいだろう。AIによってコストは削減され、表現の自由度は高くなるというメリットがある。
メタバースにおけるAI活用の可能性が語られつつも、小塩氏は警鐘を鳴らした。「手軽に表現ができる今だからこそ人間側に求められるのは、これら技術を組み合わせてどんな世界を作っていくのかを考えることです。数年前までは、3D制作費用といった『メタバースの世界を作ること』自体に手間とコストがかかっていました。そのハードルを乗り越えながらどうやってメタバースを普及させようかという問題もありました。
しかしAIによって、クオリティの差こそあれど、作ること自体のハードルは低くなってきました。並大抵のモデルで空間を制作するだけでは特異性は生まれない。AIによる効率化、インタラクティブな体験。今あるメタバースを発展させたり、従来考えられなかった新しいメタバースを作っていけるかは、引き続き人間の知恵を絞らないといけないと思います。それを形にできるツールは揃い始めています」。
 Metaverse Japanアドバイザー 東京大学大学院 情報学環 特任准教授 小塩 篤史 氏(写真提供:Metaverse Japan)
Metaverse Japanアドバイザー 東京大学大学院 情報学環 特任准教授 小塩 篤史 氏(写真提供:Metaverse Japan)
チャレンジしない企業は、未来を創れない
パナソニック コネクトの山口氏は、日本におけるAI活用の現状を、同社が参加した世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)での経験から語った。「どのセッションでもAIは必ず話題に上がっていました。各国ともにAIの実装に焦点を絞り、臆さずチャレンジしている。世界のAIに対する温度感を目の当たりにし、チャレンジをしない企業は、このAIムーブメントの中で新しいものを生み出せないし、生き残ることすらできないと感じました」と強調。
さらに、パナソニック コネクトが得意とするサプライチェーンの活用にも触れた。「海外におけるニュープロダクトはAIが絡んでいることがほとんど。特に、サプライチェーンの複雑なデータを全て取り込み、人間が理解しやすい工程指示に変換するというAIエンジンを新しく作っているようです。弊社も、工場のAIエンジンと物流のAIエンジンのデータを得ながら、サプライチェーンにおけるベストなソリューションを提供する、という所に注力しています」。
 Metaverse Japan理事 パナソニック コネクト株式会社 取締役 執行役員 山口 有希子 氏(写真提供:Metaverse Japan)
Metaverse Japan理事 パナソニック コネクト株式会社 取締役 執行役員 山口 有希子 氏(写真提供:Metaverse Japan)
小塩氏も続く。「AIは、デジタルツイン活用との親和性も高いと考えています。例えば『自動運転のロボットをトレーニング』する場合、いきなり実社会で行う前に、デジタルツイン内でトレーニングが行える工場を作る。そこで取れたデータをAIで分析し、現実世界で活かす。こういった取り組みは各業界でも多く行われていると感じます。
AIエージェントも同じで、すぐに仕事や日常生活で使っていきたい所が、ハードルや不確定要素も多くトラブルも想定される。そこでメタバースの活用ができると考えています。例えば市役所など、コミュニケーションが必須な施設をメタバース内に作ります。その中でAIエージェントを実装し、正しく機能するか試したり、対人での流れをテストする。現実だと建物の仮設費用が発生する所をメタバースで一旦構築し、実験を進めて得られたものを社会に実装していくといった流れです。AIの実験場としてのメタバース活用、という価値が高まってくると、メタバースの普及にも繋がるはず。AIの需要増加は、メタバースにとってもチャンスだと信じています」。
 パーソナリティであるMetaverse Japan 共同代表理事 馬渕 邦美 氏(右)と熱い議論が交わされた
パーソナリティであるMetaverse Japan 共同代表理事 馬渕 邦美 氏(右)と熱い議論が交わされた
「昨今のAIには、インターネットが出てきた時以上のワクワク感があります」と最後に語るのは山口氏。「メタバースの社会実装においては、まだ課題ばかり。そこを解決するテクノロジーはAIかもしれないし、メタバースとの掛け合わせかもしれない。AIとともにメタバースに関わる人たちが知恵を出し合い、テクノロジーについて議論を続け、より良い世界を作っていきたい。これがメタバースジャパンの意義でもあると考えています」。
 最後はMetaverse Japan 理事やアドバイザーが集まり撮影
最後はMetaverse Japan 理事やアドバイザーが集まり撮影
【編集後記】
メタバース業界に限らず、AIでイノベーションを起こすには「AIをいかに使いこなすか」を考えることが重要だ。そのポテンシャルをどれほど発揮し、メタバース活用への追い風にできるかは、我々人間次第といえる。AIがメタバース側に歩み寄ってくるのを待つのではなく、どう使っていくか積極的に考え、実践していく必要があるだろう。本イベントでは、業界を牽引するMetaverse Japan、そして会員が一丸となってそれらに取り組む強い意志が感じられた。