
MetaStepのパートナー企業の皆様へインタビューを通じ、近況や2025年に描く戦略・展開などを読者にお届けする新春企画。第6回目は、パートナー企業「日本電気(NEC)」さん(以下敬称略)。2024年は「【連載】新しいインフラ構築の形「DePIN」の未来を語る」でコラムをご執筆頂きました。
今回は、本インタビューの為に、社内のWeb3有識者による鼎談を開催していただきました。NECから2025年のWeb3業界はどう見えているのか!?ぜひご覧ください。
日本電気株式会社 プラットフォーム・テクノロジーサービス事業部門
バイオメトリクス・ビジョンAI統括部
Web3ビジネス開発グループ ディレクター
金融、インターネット業界にて、事業戦略策定・プロダクト開発や新規事業立ち上げを経験。NEC入社後はWeb3領域である分散型アイデンティティやデジタル証明書、生体認証、VR・メタバース、プライバシーテック、Web3コミュニティ活動などの新規事業を担当。また、国際社会経済研究所とともに、Web3ソートリーダーにも従事。

樋口雄哉
日本電気株式会社 コーポレート事業開発部門 事業開発統括部
シニアプロフェッショナル
通信事業者向けの基幹系/情報系システム開発にアプリケーションエンジニアとして従事。その後は、海外の様々なシステムインテグレーションや提案プロジェクトを経て、現在はWeb3などの新規ビジネス開発に取り組む。

井上智紀
日本電気株式会社 コーポレート事業開発部門 事業開発統括部
リードビジネスデザイナー
入社以降、研究所にて新世代ネットワークの研究に従事。シリコンバレー地域に赴任し共創型で世界初の分散型ネットワーク制御装置の設計とOSS開発をリード。帰国後ブロックチェーンの研究開発と事業化推進を経て、現在はWeb3関連の新規ビジネス開発に取り組む。

小出俊夫
2024年のWeb3・メタバース業界を振り返るとどんな年でしたか?
井上: Web3と言えば、以前このMetaStepの連載で紹介させていただいたDePIN(Decentralized Physical Infrastructure Network: 分散型物理インフラネットワーク)のように、現実世界の具体的なユースケースとセットでWeb3が語られるようになってきました。昨年は国内でも、「PicTrée(ピクトレ)」といった日本の独自性があるプロジェクトもローンチされました。実用化が加速した年だったと言えます。樋口さんの視点から見ると、2024年はどのような年だったと感じますか?
樋口: おそらく、2025年が終わるころに振り返ると、2024年はWeb3ビジネスの大きな転換期だったと言えると思います。昨年はこれまで注目されてきたNFTやSBT(SoulBound Token: ソウルバウンドトークン)だけではなく、DID(Decentralized Identity: 分散型アイデンティティ)やVC(Verifiable Credential: 検証可能な資格情報)といった技術が脚光を浴び始めました。デジタル庁や自民党web3PT(平将明衆議院議員を座長とするweb3推進のためのプロジェクトチーム)の方針にもその影響が見られますね。
小出: DAO(Decentralized Autonomous Organization: 分散型自律組織)に関しても変化の兆しがあります。昨年は4月の法改正によって合同会社型の法人設立が可能になり、それがDAOの活動を後押ししました。ただ、まだトークンやガバナンストークンを有効活用できているDAOは少なく、地方創生やコミュニティ形成が中心になっています。そういう意味で、Web3全体の注目ポイントが多様化してきた印象を受けますね。
井上: そうですね。昨年の特徴は、Web3の実用化が特定分野に留まらず、幅広い分野に広がった点だと思います。メタバースでは、VRデバイスの進化や3Dスキャニング技術、AI学習のための仮想世界の利用といった周辺技術も進化しています。メタバースという言葉にとらわれず、関連する技術全体を俯瞰して見ることが大事ですよね。
樋口: その通りですね。特に昨年は、Web3の注目がこれまでのコンシューマ向けの取り組みから、企業向けへのシフトが顕著になりました。例えば、to BのDIDやVCの利用は、企業の業務効率化やセキュリティ強化に直結する実用性があるため、多くの企業が採用を検討しています。メタバースでも、企業が独自のバーチャル空間を作り、トレーニングや製品プロモーションに利用する動きが目立っています。
小出: 企業向けの取り組みが増える一方で、DAOのようなコミュニティ主導型の個人向けプロジェクトも引き続き重要だと思います。これらがどう融合していくのか、今年以降の動きが楽しみです。
井上: グローバルな観点でも2024年は波乱の一年でしたね。11月の米国大統領選挙でトランプ氏が再選した影響で、ビットコインが過去最高値を更新するなど、暗号資産業界が大きく動きました。
樋口: そうですね。ビットコインの動きがWeb3全体に波及し、投資家の注目がさらに高まった印象があります。2025年はより成熟した市場になっていくでしょう。
2024年の貴社の代表的な取り組みを教えてください。
樋口: 昨年はWeb3とメタバースの分野で多くのプロジェクトを展開しました。まず、4月にはデジタル社員証をリリースしました。これは、マイクロソフトの分散型ID技術とNECの生体認証技術を組み合わせた次世代の社員証で、社員の働き方を大きく変えるものです。 (NECの顔認証がつくる新しい働き方 デジタルIDで人と社会と未来が「つながる」)
井上: デジタル社員証は私も勿論使っています。本社ビルの入退場がとてもスムーズに出来るようになって便利です。
樋口: 皆さん体験されているように、社員の認証プロセスが簡素化され、セキュリティが向上し、オフィスへの入退室管理や社内システムへのアクセスがスムーズになりました。あと10月には、IATA(国際航空運送協会)主催のコンタクトレストラベルに関する実証実験に参加しました。これは、空港での手続きや搭乗を非接触で行うための技術を検証するもので、NECの顔認証技術が活用されました。
小出: 本人を非接触で認識する技術は今後ますます重要になりますね。
樋口: その通りです。さらに、11月にはIISEさんと共同で「推し活」に関する調査レポートを発表しました。これは、ファン活動の実態やトレンドを分析したもので、エンターテインメント業界への新たな提案を含んでいます。そして、12月には大阪・関西万博(以下、万博)の落合陽一さんがプロデュースするパビリオンへの技術提供を行いました。具体的には、顔認証技術を活用したVCを用いることで、パビリオンでの体験やアプリをより安全に利用できる基盤を提供します。(NEC、2025年大阪・関西万博のテーマ事業「シグネチャーパビリオン」に技術支援)
井上: メタバース分野ではどのような活動を?
樋口: 11月にダイキン工業と共同で、BtoBメタバース上での空調機点検トレーニングを開始しました。これは、Microsoft Mesh上に仮想空間を構築し、サービスエンジニア向けの体験型研修を提供するものです。現場に近い環境でのトレーニングが可能となり、効率的な人材育成が期待できます。
これらの取り組みを通じて、今後も引き続きNECはWeb3やメタバースの分野での技術革新と社会実装を推進しています。
Web3・メタバースのビジネス活用の現在地をどのように感じていますか。
井上: Web3全体で見ると、まだ発展途上というのが正直なところですね。特にNFTは、様々な可能性が模索されていますが、投機的な側面が注目されてしまっているのも事実です。勿論、ユニーク性や透明性、所有権の証明といったNFTの特性を活かした実用例も着々と出てきていますよね。
小出: NFTはデジタルアートなどの売買だけでなく、イベントのチケット販売や管理、匿名性を保ちながらの本人認証、さらにはクラウドファンディングのリターンとしての活用も見られます。ただ、まだ試行錯誤の段階という印象は否めません。その「試行錯誤」の段階を抜け出すためには、やはり技術とビジネスの間に明確な接続点を作ることが重要だと感じます。DAOもその一例で、国内でもDAOの組成や運用を支援する有償サービスが出てきていますが、現状ではユーザーの細かなニーズに対応しきれていない印象があります。
井上: DAOに詳しい小出さんから見ても、まだ課題が多いんですね。ただ、一方でコミュニティ形成を課題にしている組織がDAOに注目し始めているという話も耳にします。具体的な使い方がまだ模索中とはいえ、少しずつポジティブな流れが生まれているとも感じませんか?
小出: はい、その点は大いに感じます。昨年と比べると、DAOに対する反応が確実に変わってきています。特に、コミュニティの意思決定を透明化したいとか、分散型の組織運営に挑戦したいという声が増えていますね。ただ、多くの場合、具体的な活用イメージがまだぼんやりとしていて、どこから手を付ければいいか迷っているケースが多いように感じます。
樋口: その話は非常に興味深いですね。私としては、Web3がこれから生むビジネスの可能性には非常にワクワクしています。確かに現状では市場自体がまだ成熟していないと思いますが、DAOやトークンが組織の在り方を大きく変える可能性がありますよね。従来の株式会社やトップダウン型の組織から、もっと柔軟で参加型の仕組みへ移行する、そんな未来が見えています。
井上: 確かに、Web2.0も最初はどんなビジネスモデルが生まれるのか予測しづらかったですよね。でも、利用者が増え、サービスが浸透するにつれて新しい価値が次々と生まれました。
樋口: まさにその通りです。Web3でも同じことが起きる予感があります。ただ、ポイントは、事業会社がどれだけ粘り強く待てるかですね。例えば、Web3サービスを立ち上げても、収益化までに時間がかかるケースが多いです。そこまでのインフラ整備や予算投入が鍵を握ると思っています。
小出: そうですね。メタバースにも同じことが言えそうです。メタバース内でのNFT活用やDIDの導入といったアイデアは非常に魅力的ですが、それが実際にスケールするまでの課題は多いですよね。
井上: インフラ整備やコスト面の課題もそうですが、ユーザー体験の質をどう向上させるかも重要ですね。具体的な成功事例が増えてくると状況も変わるのでしょうけど。
樋口: その通りです。私は、これからのWeb3やメタバースの成長には、業界全体での協力が必要だと思っています。特に、社会インフラの構築やガイドラインの整備は、官民が連携して進めるべきテーマですね。
そういった現在地の中で、2025年はどういった年になると予測されていますか?
井上: 2025年は引き続き進展する年になると思います。特に、物理世界との接点がこれまで以上に増え、具体的に目に見えるサービスやビジネスが台頭してくるでしょう。たとえば、ブロックチェーン上での取引が、リアルの経済活動と直結する形で利用されるケースが増えると予想されます。DePINはその典型ですね。
小出: 確かに、今までは技術の可能性を試している段階でしたが、2025年はその成果が形となって現れる年になるかもしれませんね。それとAIとWeb3の融合も注目されていますよね。
井上: その通りです。AIエージェントとウォレットを組み合わせた新しいタイプのサービス、仕組みが登場してくるでしょう。AIが自律的に資金管理や意思決定を行い、それをWeb3の技術で支えるイメージです。
樋口: そこに加えて、2025年はWeb3社会実装の元年になると考えています。私たちのような企業が2023年から進めてきた種蒔きや顧客ヒアリング、MVP開発で得た知見を活かし、いよいよ現実の社会課題にWeb3が結びついてくる年になるでしょう。特に、RWA(Real World Asset: 現実世界の資産)、つまり不動産や社債だけではない、日常的なサービスや権利とWeb3が結びつき始めると期待しています。
井上: 日常的なサービスとの結びつき、面白いですね。私はHivemapper(ハイブマッパー)や、Filecoin(ファイルコイン)のようなDePINプロジェクトを連想するのですが、樋口さんの視点からすると、例えば、どのようなユースケースが考えられますか?
 (引用:Hivemapper) 車に専用のドライブレコーダーを取り付けて運転してもらうことで、地図データを収集。データの収集に貢献したユーザーには、報酬として暗号資産HONEY(ハニー)が与えられる。世界中のドライバーの協力を得て、リアルタイムで地図を作成し、情報を更新するというコンセプトだ
(引用:Hivemapper) 車に専用のドライブレコーダーを取り付けて運転してもらうことで、地図データを収集。データの収集に貢献したユーザーには、報酬として暗号資産HONEY(ハニー)が与えられる。世界中のドライバーの協力を得て、リアルタイムで地図を作成し、情報を更新するというコンセプトだ
樋口: 例えば、イベントのチケット管理や日常の購買活動におけるNFTの利用、さらにDIDやVCの活用が挙げられます。特に2025年の大阪・関西万博では、こうした技術を実際に体験できる場が生まれると思っています。この体験が2026年以降の本格的な社会実装の礎になるでしょう。
小出: 万博でのデジタルヒューマンやDIDの活用は確かに期待されますね。それと、DAOの活用も2025年には具体的な成果が見えてくるのではないでしょうか?例えば、地域課題の解決にDAOを使い、住民参加型の意思決定を実現するような動きが進むと思います。
井上: それは非常に興味深いです。DAOを活用した地域課題解決の成功例が増えることで、参加者の動機や価値観も変化していくのでしょうか?
小出: はい。これまでは金銭的なインセンティブが中心でしたが、2025年は「地域に貢献したい」や「自分の意見が形になる喜び」など、非金銭的なインセンティブが注目されると思います。結果的に、DAOが新しい形のコミュニティ形成やマーケティング手段としても利用される流れが加速するでしょう。
樋口: そのためには、人材育成も重要ですね。Web3やメタバースの成長に必要な人材を育てると同時に、企業としての姿勢を明確に打ち出すことも欠かせません。2025年は新たな可能性を試し、次の大きな飛躍への準備を整える年になるでしょう。
井上: なるほど。社会課題に応える技術の実装と、次世代のビジネスモデルを育てるための基盤作りが進むわけですね。2025年は、Web3やメタバースの成熟が一段と進む年になると期待できますね。
小出: はい。成果が見え始める一方で、新たな課題にも直面すると思いますが、それもまた次の進化につながる一歩になるはずです。
2025年に計画している取り組みなどあれば教えてください。
樋口: 2025年は、Web3技術をさらに広範囲に活用する計画が進んでいます。特にDIDとVCを活用した施策を、空港や航空領域以外にも広げていきます。具体的には、教育、製造、金融、リテールといったさまざまな分野への応用を想定しています。
小出: DIDやVCは空港やトラベル関連で活用が進んでいますが、他の分野ではどのように展開していく予定なのでしょうか?
樋口: 例えば教育分野では、デジタル卒業証書や学生証の形でDIDを活用し、学生や教職員の認証プロセスを効率化します。また、製造業では、サプライチェーン全体の透明性を向上させるために、VCを使って製品や部品の出所や製造過程を証明することが可能です。金融やリテールでは、顧客の身元確認や信用情報の管理がDIDとVCを活用することで簡素化され、セキュリティが向上します。
井上: なるほど、非常に多岐にわたる応用が考えられているのですね。メタバース分野では、どのような計画がありますか?
樋口: 2025年には、万博での顔VCの導入結果をもとに、さらなる社会実証を進める予定です。万博では、落合さんのパビリオンの他に、顔認証を使った入場管理や決済システムを導入しますが、この技術の有効性や課題を洗い出すことが大きな目的でした。これを踏まえ、2025年には公共施設や商業施設など、より広範な領域での実証実験を計画しています。
小出: その技術が商業施設や公共空間で広く使われるようになれば、日常生活にも大きな変化をもたらしそうですね。
樋口: そうですね。そして、NECの取り組みは国内にとどまりません。2025年は、北米やAPAC(アジア太平洋)地域での展開を強化していく予定です。特に、DIDやVCは国境を越えた身元確認や信用証明に非常に有用で、これらの地域での需要が高まっています。北米では航空業界や教育分野、APACでは製造やリテールの領域でパートナーシップを拡大していきます。NECとしては、技術開発だけでなく、社会課題の解決に貢献することを目指しています。2025年は、その目標に向けた重要な年になると考えています。これからも皆さんの協力を得ながら、未来を切り開いていきたいと思っています。
最後に今年の意気込みをお願いします。
小出: 2025年も私たちにとって重要な年になると思います。特にDAOの分野では、営利企業がDAOをどのようにビジネスに活用できるのか、その具体的な成功パターンを示すことが大きな課題です。私自身もこの領域でチャレンジを続けて、市場に「これが成功事例だ」と言えるような形を作りたいと思っています。
井上: DAOをビジネスに活用する具体例を示すことができれば、業界全体の信頼性や関心も一気に高まりそうですね。私は、NFTを個人証明や認証に利用するユースケースに関心を持っています。これらを活用した現実的で役立つ成功事例を生み出したいと考えています。幸い関連する特許もいくつか取得しているので、それを基に形にしていきたいですね。
小出: そうですね。2025年にはお互いの研究と実績をさらに発展させて、社会やビジネスに接続する成果を実証する年にしたいです。お互い頑張りましょう!
樋口: その意気込み、良いですね。私たちの部門も、2025年を非常に重要な年だと考えています。Web3の技術やDAO、NFTを活用することで、これまで当たり前だった価値観や組織形態、さらには株式の概念すら変わる可能性があります。そうした新しい行動様式のきっかけを、私たち全員で作り出していきましょう。特に、社会にインパクトを与える成功事例を一つでも多く実現することが、2026年以降のさらなる飛躍につながると思っています。2025年を、Web3を通じた未来の第一歩として、しっかりと形にしていきましょう。よろしくお願いします!


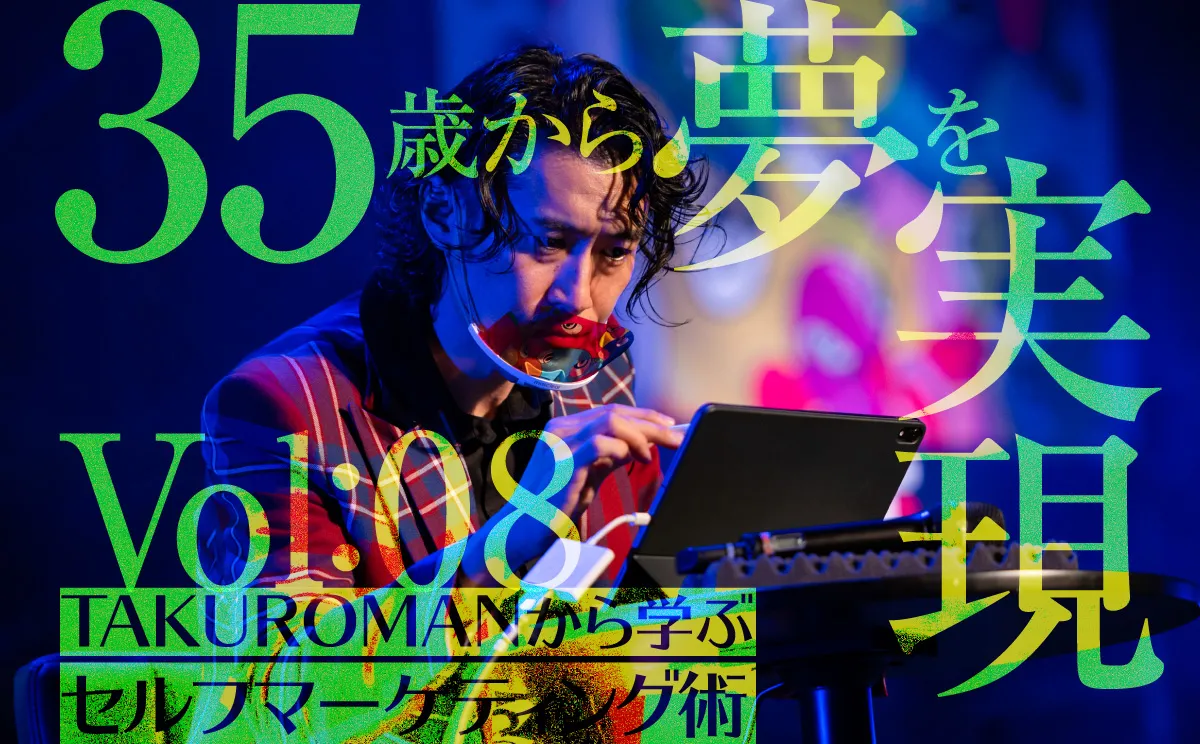
.jpg)








