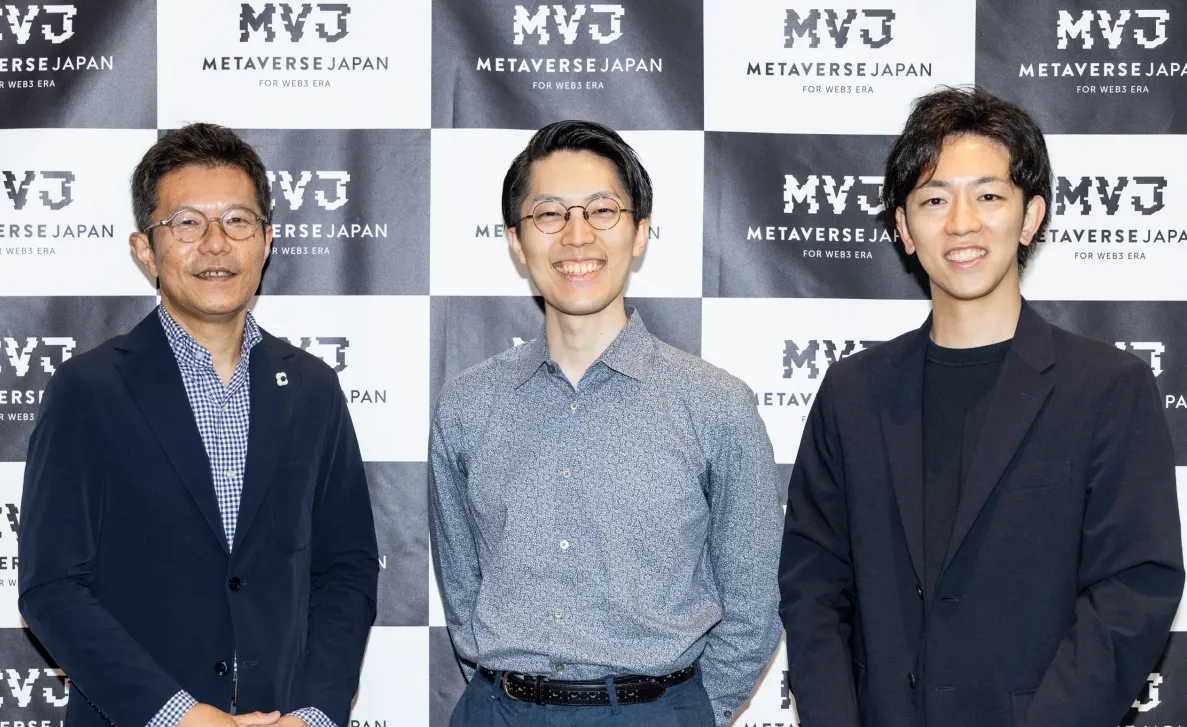DePINは(Decentralized Physical Infrastructure Network)の略語で、日本語で「分散化された物理的なインフラネットワーク」を意味します。ブロックチェーンと暗号資産を活用した、新しいアプローチとして注目を集めています。一見すると難しそうな印象ですが、すでに多くの導入事例がある、注目の技術です!
実際にどのような仕組みで、どのように将来性が期待できるのかわからない方向けに、DePINの基礎知識から将来性、課題を詳しく解説します。最新技術に興味のある方は是非参考にしてください。
DePIN(ディーピン)とは?
DePIN(Decentralized Physical Infrastructure Network:分散型物理インフラネットワーク)は、暗号資産を報酬として物理的なインフラネットワークを構築する分散型プロダクトの総称です。
仕組みを簡単に説明すると、個人が持つ「物理的資源」を、他社に提供し、報酬として暗号資産が支払われます。(何かを手伝ったら報酬がもらえるようなイメージです)
例えば、DePINを活用した地図アプリプロジェクトHivemapper(ハイヴマッパー)では、個人が所有する車に専用のドライブレコーダーを装着して走行することで道路の情報データを提供し、報酬として暗号資産HONEYを受け取ります。
.jpg) (引用:Hivemapper)日本でもすでに地図データが広く収集されている。
(引用:Hivemapper)日本でもすでに地図データが広く収集されている。
地図を利用するユーザーは、一般的な地図アプリでは提供されないニッチな土地の情報を閲覧できるだけでなく、地図情報もリアルタイムに更新されるため質の高いサービスが受けられるのです。
地図アプリの他に、余ったデータを共有できるFilecoin(ファイルコイン)や、GPUリソースを共有できるRenderNetwork(レンダーネットワーク)などが挙げられます。
このように、個人が持つ資源を有効活用するための新しい仕組みがDePINと呼ばれているのです。
DePINの将来性
DePINは暗号資産を報酬として活用することで、これまで実現が難しいとされていた大規模なプロダクト開発を可能にする新しいビジネスモデルとして期待されています。従来の手法とは異なり、莫大な先行投資や中央集権的な管理を必要とせず、コミュニティの力を結集してインフラを構築できる点が大きな利点です。
DePINに基づく分散型アプリケーションでは、貢献者への暗号資産報酬がゲーム化され、プロダクトの使用によって暗号資産が消費される仕組みを持ちます。これにより、参加者全員がコミュニティに貢献し、提供するサービスに対して収入を得られる新たな経済参加の時代を切り開く可能性を秘めています。
DePINは、これまでのインターネット(Web2.0)から新しい時代(Web3.0)への進化を物理的に具現化する一例として、大きな期待が寄せられているのです。
DePINの課題
DePINの課題として、報酬と運用コストのバランスを取ることが重要となりますが、ユーザーの参加意欲が低い中でこのバランスを達成することは容易ではありません。提供するサービスや製品の品質を高く維持し、既存のソリューションよりも優れた価値を利用者に提供できるよう努めることが求められます。
DePINプラットフォームが提供するサービスや製品の品質が既存の中央集権型のソリューションと比べて劣ってしまうと、たとえコスト面で優れていても利用者にとっての魅力は薄れてしまいます。
また、DePINネットワークの参加者に支払われる報酬のほとんどがプラットフォーム独自のトークンで行われるため、価格変動が大きいと長期的に利用者の参加意欲に影響を与える可能性があります。
DePINプロジェクトが成功するかどうかは、提供されるサービスに対する需要が明確に特定できるかどうかにかかっていると言えるでしょう。
まとめ
DePINは、個人が持つ資源を共有できる新しいネットワークとして注目を集める新技術です。透明性と公平性の高いプラットフォームを実現する可能性を秘めていますが、ユーザーの参加意欲を高める仕組みの構築やセキュリティ、法規制などの課題もあります。
しかし、普及が進めば将来的に多くのサービスがDePINに置き換わることも考えられます。今のうちに深く理解しておくことで、今後自社のビジネスにDePINを活用する際にいち早く対応できるでしょう。